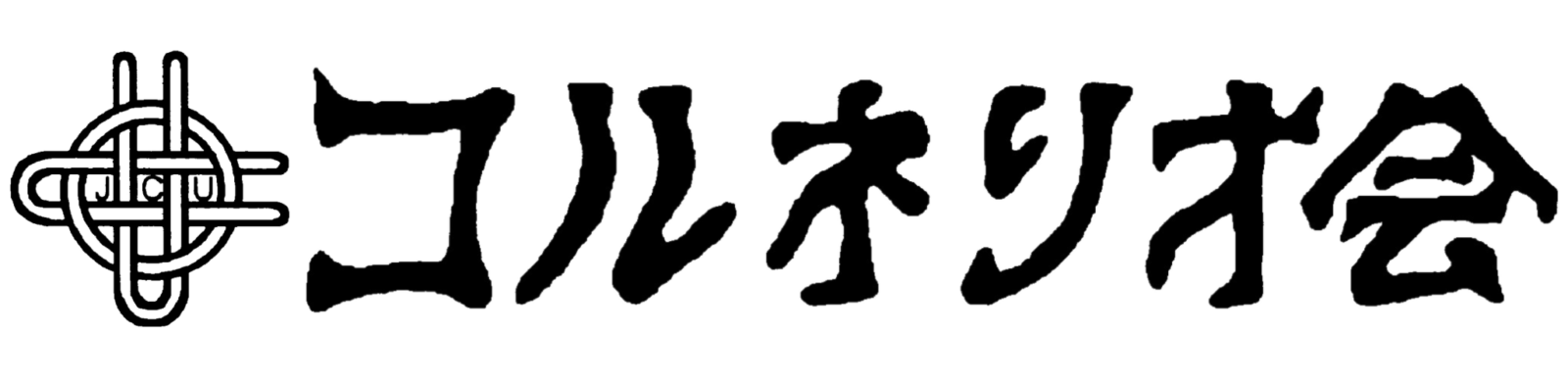軽井沢新年聖会に参加して
会員 石川 信隆
今年(2013年)も元旦礼拝のあと、1月1日-3日ま
で軽井沢新年聖会に参加することができました。昨年
末から、腰の痛みが激しく、参加出来るかどうかと心
配しましたが、思い切って行って参りました。今年の
テーマ「癒し主イエス」にふさわしく、メッセージの
前は聖歌 476 の「やすけさは川のごとく」が何回も何回
も歌われ、聖霊が会場に流れるのを感じました。
今年はメッセージの概要資料が配布されず、ただ平
野耕一先生がその時その時、聖霊に導かれるままにメ
ッセージを語られました。その中で私が特に印象に残
ったみ言葉は、「たとい私たちの外なる人は衰えても、
内なる人は日々新たにされています。」(コリント人へ
の手紙第二4章16節)のみ言葉でした。
ここで、「外なる人」とは、例えば、肉体です。そ
れは現在いかに元気で若々しくても、やがて時の流れ
と共に必ず衰えていきます。 それは誰もがいずれ経験
するでしょう。「外なる人」は衰えるのです。特に今
年は腰の痛みで、肉体の衰えを痛感しました。階段を
上がるにも、会場へ行くときも痛みをこらえ、足を引
きずって行きました。しかし、神を信じる者には、決
して滅びない「内なる人」が存在しているのだと教え
られました。 その「内なる人」は、ただ単に死んでも
滅びる事のない永遠の命を持つというだけではなく、
地上の人生においても「日々新たに」リフレッシュさ
れ、成長し、喜びに満たされるのを私達は体験すると
いうのです。
では、「内なる人が日々新たにされる」にはどうした
ら良いでしょう。その秘訣は、第一に「主の教えを喜
びとし、昼も夜もそのおしえを口ずさむ。」ことだと
教えられました。「主の教え」つまり聖書の「み言葉」
を「喜び」とするということが、詩篇1篇によると「幸
いな」歩みであり、「何をしても栄える」というので
す。
「喜びとする」という言葉は、「み言葉を楽しむ」
ことです。「み言葉を楽しんでいれば」、毎日聖書を読
みたいと思うようになるそうです。朝読んだみ言葉を
頭の片隅におきながら一日を過ごすのです。それが「昼
も夜もそのおしえを『黙想する』『思い巡らす』」と
いうことの意味です。そうすれば自然と、み言葉を自
分の生活に適用していけるようになるのだと教えられ
ました。
そして第2は、み言葉を信じて素直に行動を起こす。
実行することです。
その例として第2列王記5章にあるナーマン将軍の
らい病が癒されたお話しをされました。預言者エリシ
ャから「ヨルダン川へ行って7たびあなたの身を洗いな
さい。」というみ言葉をいただいたナーマン将軍でした
が、初めはプライドが許さず、そのみ言葉に従う事が
出来ませんでした。しかし、最後は自分の高慢さに気
付き、自分よりも地位の低いしもべ達の忠告を素直に
聞き入れて、神のみ言葉に従いました。そこで病はた
ちどころに癒されたと云うお話でした。
この新しい一年、み言葉を口ずさみ、み言葉を楽し
んで、素直な心で神様に従って歩んで行きたいという
思いを強くして帰ってまいりました。
ブラジル・アリアンサ宣教の過去・現在・未来(その3)
会員 圓林 栄喜
4 今後の展望
(1)人を変える場所
アリアンサはサンパウロから 600km も離れた果
てしなく広がる緑の大地の中にあります。その1
でも書きましたが、多くのキリスト者が送り込ま
れ、乳と蜜の流れる里の建設を目指しました。そ
れから89年が過ぎました。この地は多くの聖徒達
によって福音の種が蒔かれ祈られた地でもありま
す。下桑谷牧師はこの地で何人もの日本人の若者
を預かりました。彼らはこの地に来て、悩み、苦
しみから解放され、学校や社会に復帰したり、献
身したり、宣教師になり再びアリアンサの地に来
て伝道に従事している方もいます。下桑谷牧師は、
「私は底知れぬ魅力を持つブラジルの大地(この
大地は私を包み込んでくれる母なる大地であり、
はたらくエネルギーを与えてくれる大地でもあ
る。)そして貧しさを感じさせない人々、私のよう
な者でも喜んで受け入れ働かせてもらえるブラジ
ルに少なからず心惹かれている。」と言います。
(2)「アリアンサ聖書学校」
下桑谷牧師が日本にいた頃、悩める青少年を目の
当たりにしつつ助ける力を持たず果しえないままブ
ラジルへ行きました。それから22年の間にアメリカ
シカゴの「クリスチャンアカデミー・スクール」や
ジョージ・ミュラーの「孤児の家」、「北海道家庭学
校」などの研修を積み重ねます。また、順を追うよ
うにみことばが示され、ついに土地が与えられ、プ
ラン作成へとこぎつけます。
「森と土と聖書」を土台とし、集う若者に「健全
な戸外運動を与えるとともに食物の供給に役立て、
自給生活を教える」ことを目的として、その名を「ア
リアンサ・クリスチャン・アカデミー『アドラムの
家』」と命名します。しかし、3.11を機に組織表
のアドラムの家をアリアンサ・キリスト教会付属の
「アリアンサ聖書学校」に改め、希望者をできるだ
け早く招けるように準備を進めています。これまで
のところ祈りは聞かれ、旧家屋、電気、水道等の修
理及び耕作地の整備を終え、野菜等の作付を始めて
います。また、日本語教育は継続しており、聖書の
初級教育も実施しています。
5 最後に
3回にわたり、ブラジル・アリアンサ宣教の過去・
現在・未来について説明しました。
「百聞は一見に如かず」です。人を変える魅力の
あるここアリアンサに是非多くの日本人が訪問され、
神と出会い、神からの新たなエネルギーを与えられ
ることを心から待ち望んでいます。ご関心のある方
は、下記までお問い合わせください。
また、先回のNL131号でお願いしましたアカデ
ミーの土地取得のための経費 100 万円は祈りと献金
により満たされました。コルネリオ会関係者からも
献金が奉げられました。お祈りと支援に心から感謝
申し上げます。ありがとうございました。
IGREJA EVANGELICA ALIANCA
REV.HIROSHI SIMOKUWAYA
C.P.543- PRIMEIRA ALIANCA
16800-973-MIRANDOPOLIS-SP-BRASIL
AMCF東アジア会長 韓国海兵隊退役中将
TEL&FAX 18-3708-1265
自衛ということ
海軍兵学校102分隊会員 西澤 邦輔
矢田部稔兄から、2012年12月29日に発行さ
れた海軍兵学校102分隊会報(第22号)の「自衛とい
うこと」という記事の情報提供がありましたので主要
な部分を抜粋して掲載させていただきます。
(1)戦後、文科系の学問の中では歴史学が最も事実
に即しているので最も客観的であるかのように見なさ
れ、それゆえ、唯物的であればあるほど、その史観は
科学的に信頼できるかのように期待された。
しかし、歴史学の素材である資料を選択する段階で
既に歴史家の価値観がものを言う。資料を解釈し組み
立てるに当たっては尚更である。勿論、歴史的認識の
深まりによって思想が深められることはあろうが、歴
史が思想を生むよりは、思想が歴史を生む。歴史は科
学であるよりは思想である。
言い方を変えれば、一つの思想をもって歴史を見れ
ば、その思想を証明する歴史的事実は必ずある。だか
ら、これこれの思想は人間の歴史に照らして正しいと
いう言い方は常に可能である。だから、正しい歴史観
が無数にあって、相互に矛盾し合う。その中からどれ
を選び取るかは、結局その人の世界観の問題に帰する。
(2)明治以降の富国強兵策は西洋先進国のアジア植
民政策を排除することが、つまり自衛が、直接喫緊の
目的であり、そのための軍備軍隊の創設発展は至極当
然のことであったはずである。ところが、正規の国家
的軍隊が創設されて以降、その存在自体が無言の防衛
になったであろうことは認めるが、自衛のための戦争
といえるものがあったであろうか。すでに日清戦争も
自衛のためとは言い難いのではないか。その戦後処理
の台湾併合がその事を結果的に物語っているように思
う。しかも、道を逸れていて結果がうまくいくとろく
なことはない。それが、それ以降の軍隊の存在意義を
自衛から遠ざける転機となったのではないか。(軍隊が
自衛の姿勢を維持するためには国民の価値観が一定レ
ベル以上に保たれなければならない。)
例えば、貧乏所帯へ大金が転がり込んで急に余裕が
できると、堅固な道徳性がない限り、忽ち物心の自己
制御が効かなくなって果てしのない欲心に振り回され、
生活は乱れ、価値観まで変わってしまうようなもので
ある。そう見れば明治80年の歴史は、余りにもお決
まりのコースである。遂に本土決戦まで追い詰められ
たが、これは自衛のためとはいえない。その意識もな
かった。先に手を出した喧嘩の最後の意地を見せるた
めにすぎなかったのではないか。
(3)日本の歴史には都市国家の経験がない。つまり、
市民自己責任国家の市民であった経験がないのである。
戦争は殿様がするものであって、百姓町人には、とば
っちりはあっても、責任関係はない。明治以降も心理
的には大差はなく、なるほど市民も徴兵されて軍隊の
構成員とされたが、それは殿様に徴用された庶民の場
合と同様、「天皇のために」徴用された臣民であって、
そこに要求される犠牲が国民の自衛のためであるとい
う感覚も自覚も事実もなくて、ただ「大君の醜の御盾」
としての感傷的大義意識によって、為すことすべてを
自己正当化していただけのことである。そのような
我々の立場からすれば、実際あの頃、「天皇のため」と
いう犠牲の目的的人格を持たない民主国米国人は、何
のために命を捨てて我々と戦うことができるだろうか
と、大いに疑問に思われるものである。
戦後の再軍備問題がなかなかすっきりしないのは、
自衛という感覚が日本人には生理的に納得できないか
らではないか。軍隊とは、「天皇の軍隊」、せいぜい国
家権力のためのものであって、庶民にはないにこした
ことはない程度のもの、このような自衛への無感覚と
偏見が、軍事への無視反感になっているのではないか。
朝鮮戦争を機に、急きょ「反憲法、超法規的」に軍隊
が作られたが、60年経った今も認知されない私生児
の取り扱いである。このことがすでに、あるいは今後、
どのような後遺症を国民の運命に残すことか。
(4)海兵77期機関紙「江田島」最新号(平成22
年6月発行第91号)に、75期生徒で元最高裁長官
三好達氏が、平成15年建国記念日講演要旨を「日本
再生の道」と題して寄稿している。その中に5項目の
「わが国の(憂うべき)現状」が挙げられ、一々読み
ごたえがあるが、その最後「国防意識の欠如」には、
こんな言葉がある、
「・・平和主義を憲法に掲げ、戦争をしない意思を
表明していれば、一国の平和は保たれるという思想が、
我が国を風靡しています。・・国家にはどうしても果た
さなければならない究極の任務がある、・・国民と国土
を外敵の侵略から護ること、これが究極の任務で
す。・・わが国の国民は、このような意識が希薄であり、
為政者もこのことを強く申し述べないのが現状であり
ます。かくして、・・遂には、我が国民が、我が国土の
中から、他国の工作員によって拉致されるという事件
まで生じています。・・国民が国民として国を護らない
と悲惨な目にあうということを、もっと教えなければ
ならない。・・」
書籍紹介
最近出版された、いくつかの書籍があります。自衛
官として、クリスチャンとして感じることがいろいろ
あると思いますので、お読みいただき、感想などいた
だければ幸いです。
1 『戦争は人間的な営みである―戦争文化試論―』
(石川明人 著 並木書房)
戦争は悪である。誰もが平和を願う。だが、それ
にもかかわらず戦争や軍事には人を魅了するものが
ある。なぜ人間は「戦い」に惹きつけられるのか?
なぜ人は「兵器」に興味を抱くのか?「戦争」は純
然たる悪意」のみの産物ではない。本当に平和につ
いて議論をするのならば、軍事は「文化」であり、「戦
争は人間的な営み」であることを素直に認めなけれ
ばならない(著書紹介文抜粋)
著者:昭和49年東京生まれ。北海道大学 助教
博士(文学)宗教学・戦争論
主論文「アメリカ軍のなかの聖職者たち
従軍チャプレン小史-、「戦艦大和からキリ
スト教へ-吉田満における信仰と平和-」
2 『武士道とキリスト教』
(笹森建美 著 新潮新書)
に呼応する―武士道とキリスト教の根幹には、驚くべ
き共通点があった。牧師である著者は、日本屈指の剣
術家というもうひとつの顔を持つ。「格好だけ良いの
は本物でない」「魂とは私という人格である」・・人の
生死を問う二つの「道」をきわめて得た、今日本人に
必要な智恵(著書紹介文抜粋)
著者:昭和8年青森生まれ。駒場エデン教会牧師
小野派一刀流、大長刀直元流、居合神無想林
崎流宗家を務める。早稲田大学哲学科、米国
デューク大学大学院神学部卒業
中村誠一兄のためにお祈りください。
中村誠一兄は2月に脳内出血で倒れ入院中です。3
月に沖縄へ引っ越される予定でしたがリハビリが必要
です。癒されるようお祈りください。
2013年度コルネリオ会総会案内
2013年度のコルネリオ会総会を次の予定で実施
します。総会会場として今回は馬橋キリスト教会の一
室をお借りして開催することになりました。ご都合の
つく方は参加ください。
日時:2013年5月11日(土)
1330~1630
場所:馬橋キリスト教会
東京都杉並区高円寺北4-24-11
連絡先:圓林(えんりん)03-3312-8043
献金感謝(2012.12.1-2013.3.31)
いつもコルネリオ会を覚えていただき感謝致します。
吉田靖、矢田部稔、長濱貴志、川村功、海野幹郎、
今市宗雄・敬子、石川信隆、大久保真道、
圓林栄喜・さゆり、加瀬典文・真弓、伊東忠臣
廣田具之、山下和雄
新年度を迎え、新たな出会いが生まれていると思い
ます。出会いを大切にし、良きキリストの香りを放ち
たいものです。
(編集子)