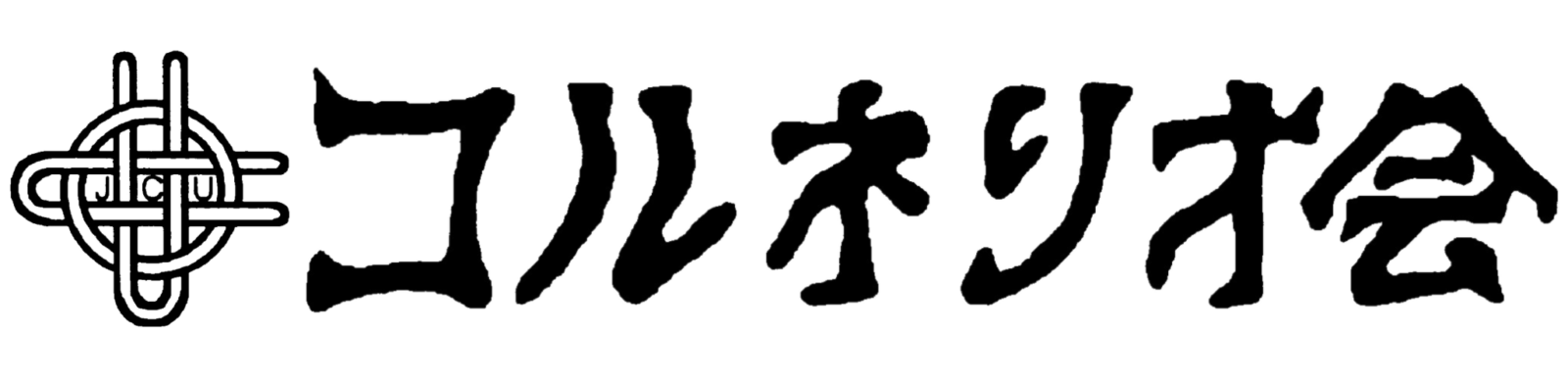家族の軌跡(ファミリーヒストリー)
コルネリオ会 会員 圓林栄喜
1 平和の礎に刻まれた祖父
NHKで「ファミリーヒストリー」という番組が
ある。著名人の家族の歴史を本人に代わって取材し
本人に紹介してくれる番組である。
この冬、私のファミリーヒストリーともいうべき
小旅行をした。母方の祖父の名が刻まれた沖縄の平
和の礎を母とそして私の家族と訪問した。
平和の礎に母方の祖父の名が刻まれたのは20
04年(平成16年)である。経緯を確認すると、
軍人であった祖父は予備役であったが、召集され沖
縄戦に参加することになったようである。ところが、
沖縄戦に参加する途中に祖父が乗っていた船が火
災で沈んでしまい、逃げ遅れたか脱出できなかった
かが理由で亡くなった。このため沖縄戦で直接亡く
なったわけではなかったため遅くなったようであ
る。平和の礎には24万名を超える方々の名前が刻
まれている。故郷の墓でみる祖父の名前が確かにそ
こには刻まれていた。祖父の顏は写真でしか見たこ
とはない。母は3人姉妹の末っ子で戦争未亡人の祖
母を助け懸命に働いた。戦死ではなかったせいか、
軍人恩給の支給も周囲の同様の境遇の方々に比べ
ると遅かったと母はいっていた。決して裕福な生活
ではなく、2人の姉は中京地区に嫁ぎ、残された体
の弱い母の面倒を見るため、結婚など考えることも
なく父と出会ったようである。父はそのような母の
状況を理解したうえで結婚を申し込んだ。結婚後母
方の祖母は心臓が弱く長い入院生活から特別養護
老人ホームに入所する。物心ついたころにはベッド
の上の祖母しか記憶には残っていない。
2 バンコクで終戦を迎えた祖父
コルネリオ会 会員 圓林栄喜
父方の祖父は徴兵で、山砲部隊の兵士として中国
武漢からインドシナ半島を延々と歩き、バンコクで
終戦を迎えた。復員後は山を開拓してみかんを栽培
し、父とともに農業に従事した。時おり、近所の戦友
と昔話に花を咲かせ、戦友会に出かけていく後姿を
覚えている。防大に入ってからであるが、帰省の折に
よく戦争当時の話を聞き、なつかしそうに話してく
れた。父が交通事故で亡くなったときは、まさか息子
が先に死ぬなど想像もしていなかったと思う。しか
し、半年後に我々家族が異動で1年半と言う短期間
ではあったが、実家の近くに住むようになり、母、祖
母も含め非常に近い関係になった。おかげで、子ども
たちは毎年の帰省を楽しみにしてくれている。
3 神の絶妙な計画
さて、平和の礎に刻まれた母方の祖父の名前を見
つめながら、別の思いが湧き上がってきた。
もし、母方の祖父が元気に沖縄から帰ってきたら、
自分はこの世に生を受けていただろうかと。もし父
方の祖父が戦死していたら、自分はこの世に生を受
けていただろうかと。
さらに、もし父が交通事故で亡くならなかったら、
このような機会が与えられただろうかと。実に人は
父母から生まれ、父母もまたその父母から生まれ、
それぞれが体験する様々な出来事の中で脈々と命
が受け継がれる。
戦争によって失われた命もあれば、戦争がなけれ
ば生まれなかった命もある。我々の人生はやはり神
の絶妙な計画の中で進められ、またいつ、だれが、ど
のように神に出会うかも絶妙なタイミングである
ことを改めて感じた小旅行であった。この世に生を
受けた者は自分の身に起こる出来事を偶然でかた
づけることなく、その家族の様々な思いを胸に、そ
の瞬間、瞬間を誠実に歩むべきではないだろうか。
4 聖書に見るキリストの系図
旧約聖書のルツ記でナオミがモアブの地からベ
ツレヘムに戻り、ルツが落穂拾いに出かけた畑が
「はからずもエリメレクの一族に属するボアズの畑
のうちであった。」と記されている。
異邦人のルツが、イスラエルの地に導かれ、その
末裔がイエスであることは新約聖書のマタイの福
音書が記している。その系図の中には、ルツとボア
ズだけでなく、ユダとタマル、ダビデとウリヤの妻
バテ・シェバなど現代でもスキャンダルになるよ
うな人々も含め、様々な人物がイエスの誕生までに
名を連ねる。壮大なファミリーヒストリーがそこに
ある。何故そのような人々がイエスの誕生に関係す
るのか。榎本保郎師の「一日一章」には「この系図の
中に、福音そのものが証されている。数の中に入る
ことのなかった人、自分が過去に犯した汚名がいつ
までも消えず、その汚名の中に滅んでいかなければ
ならないような人が、イエス・キリストのゆえに光
栄あるものとされるのである。」とある。最悪の事態
が最高の栄誉に変わるなど人間には理解できない。
しかし、あえて神はそのような計画を立てられたの
である。
5 与えられた人生に感謝
一度しかない人生である。嬉しいこと、楽しいこ
と、悔しいこと、悲しいことすべてがあり、誘惑もあ
り、失敗も成功もある。そのすべてで私の人生であり、
神が与えてくださる時なのだ。クリスチャンになっ
たことで、人生の受け止め方が変えられたことは感
謝である。
神の緻密な計画を信じ、出会いを大切にするとと
もに、いつもその導きに感謝する者でありたいと思
う。
「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。す
べてのことについて感謝しなさい。これがキリス
ト・イエスにあって神があなたがたに望んでおら
れることです。」Ⅰテサロニケ5:16~18
ピューリタンについて(その2) ピューリタンの特色
コルネリオ会会員 長濱 貴志
前回の投稿では、ピューリタン運動の概要を歴史
上の出来事を中心に整理した。今回は、ピューリタン
の特色について整理してみたい。
前回のピューリタン運動の概要において触れたよ
うに、カトリックの形式主義、権威主義に不満を持ち、
聖書の教えに立ち返ろうとした群れは大陸に亡命し
た。そこで、彼らは大陸での宗教改革が見事に進展し
たことをつぶさに見た。そこで英国でもその改革を
期待しつつ戻ったが、英国国教会が宗教改革におい
てカトリックの残滓を残していたことに満足できず、
純粋化すなわちピューリファイしようとして立ち上
がった。ピューリタンという名はこのような運動の
動機に由来している。カトリック要素の何がいけな
いというのか。何を目指したのかを考えながら二つ
の側面から特色を考察したい。
(1)礼拝的側面からの見た特色
◯ 聖書的礼拝
彼らは、聖書的礼拝を求めた。カトリックの礼拝に
は、魂の救済に繋がるところが少ないと見たのか。権
威主義、形式主義への批判及び免罪符等救済手段へ
の疑い等があったと思われるが、ピューリタンは礼
拝の原理が聖書の教えに忠実となるように、カトリ
ック的要素を排除する。
ウェストミンスター小教理問答に見られるが、「
唯一の神を礼拝し、その他の偶像を崇めない事、唯一
の神に栄光を帰すること」を戒めとしている。
また、「人生の目的は、神に栄光を帰すること。神を永
遠に喜ぶ事」としている。これらから、人生の目的は、
礼拝において唯一の神を崇め、礼拝し、神に栄光を帰
することとなる。
そして、使徒2:41-42にあるように、「教えを堅く
守る」、「交わりをする」、「パンを裂く」、「祈る」ことが
初代教会からなされてきていた。これを礼拝に関す
る聖書的教えと捉え、次の6つを実践する事が大切
にされた。①聖書の言葉を講解する説教、②聖餐式・
洗礼式などの聖礼典、③賛美④祈り⑤教育(カテキ
ズム)⑥信仰的訓練である。特に魂の救いに繋がる
①②④を大事にした。
祈りについては、決められた言を口に出して祈る
のではなく、自らの想い考えを自由に口にして祈る
ことが許される。
説教について言えば、聴衆は礼拝に出席するにあ
たり生活における適用が求められる。聖霊の導きに
よる聖書の理解と生きることへの適用を求めて礼拝
に臨み、生活に戻って行った。そして、聖書の教えの
日常生活への適用と実践することが礼拝に出席し、
聖礼典にあずかる前提ともなった。
これらの考え方及び礼拝での信徒の態度は、私が
集っている教会が実践している事であり、身近なこ
とである。
(2)信仰的態度の側面から見た特色
◯ 黙従的信仰の否定
黙従的信仰とは、信者が司祭等階級上位者の教えに
唯々諾々と従うという事である。当時、聖書は一般人
に対しては入手困難であり、その聖書を自分自身の力
で読み解くことは困難であった。教える側に圧倒的な
アドバンテージがあり、しきたりに傚う事は普通であ
ったろうと思う。この黙従の意味するところは、権威
にすがる信仰を上から強いられること、そして救済が
その権威に服従するところにあると信じ込む平信徒
の相互依存関係のことである。ピューリタンは、この
絶対的な相互依存関係を克服していくところに特色
がある。これは、信徒が牧師同様の信仰に訓練されて
いくところまでも追求する事になる。
以上二つの側面から見てきて、ピューリタンは聖
書、精霊による力を得て、礼拝様式、信仰的態度を常
に変革することを名前の由来通り進めてきた。彼ら
の礼拝様式及び信仰的態度を受け継いでいる我々現
代プロテスタント信仰者は、この力を社会の様々な
分野に発揮し今も改革を推進する原動力となりうる
と言えないだろうか。
ピューリタンに関する考察、そのために参考とする
分野は深く広い。今後も学びを継続して、紹介してい
きたい。
米国ワシントンDC訪問記―岐路にあるキリスト教大国
会員 関 博之
平成29年2月20(月)から3月3日(金)までの
間、米国の首都ワシントンDCに滞在しました。今回
の渡米は自ら計画し、少額ながら研究助成金をいただ
きながら実現できたものでした。本稿ではクリスチャ
ンの視点から、米国訪問の感想についてお話しします。
これは米国全般にわたって言えることなのですが、
ワシントンDCは、法律や規則があるわけでもない
のに、人種や階層ごとの「住み分け」が顕著な都市で
した。白人、黒人、外国人が住むエリアが、それぞれ何
となく決まっているというような感じです。教会に
ついても、白人エリート層が通う教会、黒人が通う教
会、ヒスパニック系が通う教会、日本人用の教会まで
あり、互いに干渉しないことを暗黙の了解としてい
るようでした。日本のクリスチャンがこれを聞くと、
何となく冷たいというイメージを持つかもしれませ
んが、彼らにしてみれば自分と似たような境遇の者
が集う教会を選択できるというメリットがあるよう
です。そもそも米国の歴史を見てみると、プロテスタ
ントとカトリック教徒たちの衝突、黒人に対する差
別、移民に対する偏見など、「多様性」(diversity)か
ら起因する問題と常に背中合わせでした。住み分け
は多様性の中での平穏を保っていくための知恵だっ
たのかもしれません。そのような環境下で、米国をひ
とつにまとめているのが、1ドル札紙幣に「神の名の
もとに」(In The God We Trust)と書かれていること
からも分かるように「宗教」であり、その意味で、米国
はキリスト教大国であるとも言えます。「住み分け」
と「宗教」のバランスが米国の秩序を保っている重要
な要素なのです。
さて、私が帰国する前日の3月2日に、毎年恒例の
国家朝餐祈祷会(National Prayer Breakfast)がワシン
トン・ヒルトンホテルで実施され、トランプ大統領と
ペンス副大統領が政権発足後、初めてこれに参加しま
した。トランプ大統領は宗教団体が政治活動をした場
合は税制優遇措置を中止する法律(いわゆる『ジョン
ソン条項』)の撤廃、ペンス副大統領は自身の職務指
針聖句として、エレミヤ書第29章第11節を掲げてみ
せるなど、トランプ政権は明らかに宗教団体寄りの姿
勢を見せたと、米国内のメディアは一斉に報じました。
私はこのニュースを現地で聞いたとき、複雑な想いが
しました。というのは、米国で宗教団体が政治的な力
を持つようになると、国内の秩序を担ってきた(政治
と宗教の)「住み分け」と「宗教」のバランスに変化が
生じることが予測できたからです。神は米国を何らか
の形で変えるご計画をお持ちなのだなと、この時、強
く感じました。ただそれが良い方向に行くのか、悪い
方向に転ぶのかは、現段階では予測不可能です。その
意味で、米国は現在、岐路に立つキリスト教大国にな
っているのだと思いました。
岐路に立つ米国は、同盟国である日本にとっても他
人事ではありません。そしてそれが日本にとって良い
方向に行くのか、悪い方向に転ぶのかも、現段階では
全く分かりません。しかし、我々クリスチャンがする
べきことは明確です。それは「祈る」ことです。聖書に
「こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は
彼のために、神に熱心に祈り続けていた」(使徒の働
き第12章第5節)と書かれてあるとおりです。米国
のために、そして米国にいる兄弟姉妹のために祈るこ
とが、今の我々にとって最も大切なことなのだと思い
ます。あとは主に委ねるのみです。
米国は今、主のみ手によって大きく変えられようと
しています。わずか10日間ほどの滞在でしたが、そう
確信することのできた、本当に有意義な渡米でした。
2019AMCF東アジア大会に向けて
~アンケートへの協力依頼~
2019 年にAMCF東アジア大会を開催するべく
検討を始めました。東アジア大会の日本での開催は
1986 年(市ヶ谷)、1995年(池袋)、2002(市ヶ
谷)、2010年(成田)に引き続き5回目になります。
今回は努めて多くの防衛関係キリスト者が参加
できるように日程と場所を検討しています。時期に
ついては8月13日~15日のお盆の時期もしくは9
月3日~5日のいずれかで検討しています。
場所については、日光、成田、横浜等が候補になっ
ています。日光は「オリーブの里」、成田は前回実施し
た「マロウドホテル」、横浜は現在調査中です。都内は
空港からのアクセスは良いのですが、経費的に満足
のいく施設がないのが現状です。
国内の参加希望状況を踏まえ開催規模、時期、場所
を早めに決定したいと考えております。つきまして
はコルネリオ会ホームページ
「http://jmcf.s302.xrea.com/index.html」にアクセスの上、
「2019年AMCF東アジア大会アンケート」欄を
クリックし、パスワード「2019」を入力してアンケート
に回答ください。締め切りは2017年5月31日までと
します。 ご協力よろしくお願いいたします。
編集子
献金感謝(2016.12.1-2017.3.31)
いつもコルネリオ会を覚えていただき感謝致します。
中岡一秀、松山曉賢、今市宗雄、矢田部稔、
西澤邦輔、滝口厳太郎、谷 二郎、玉井佐源太、
河野行秀、圓林栄喜・さゆり、石井克直、芝 祐治
木下真由美、加瀬典文、長橋和彦、 常盤 一崇、
石川信隆、廣田具之